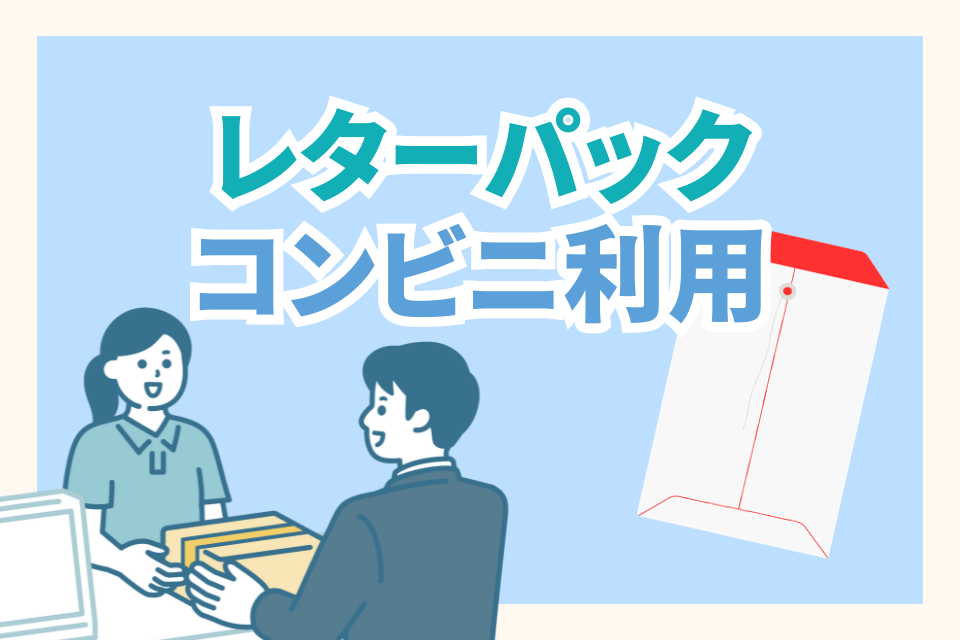レターパックは、専用封筒を購入することでさまざまな荷物や信書も全国一律料金で送れる日本郵便のサービスです。
土・日曜日、休日も含め、毎日配達が可能で、郵便物の配達状況を確認する追跡サービスも利用できます。
レターパックが購入するには
はじめに、発送に必要となるレターパックの専用封筒はどこで購入すればよいのでしょうか。
最寄りの郵便窓口
営業時間内であれば最寄りの郵便窓口での購入がおすすめです。また、通常の郵便窓口の営業時間は平日9時~17時ですが、ゆうゆう窓口であれば平日の時間外や休日でも購入できます。
郵便局のネットショップ
レターパックをまとめ買いしたい場合には、郵便局のネットショップが便利です。20枚から購入が可能で、ひとつの届け先の注文金額が5,000円以上であれば送料は無料となります。
ECサイト
楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピングなどのECサイトでもレターパックが購入できる場合があります。ただし、通常よりも高値で販売されていることもあるため、金額には注意が必要です。
ECサイトでは、キャンペーン期間を狙うと、ポイントの還元ができます。
フリマサイト
メルカリ、ヤフオクなどフリマサイトにもレターパックは出品されることがあります。この場合、通常よりも安価に入手できることもありますが、対応のスピードは出品者によって異なります。
コンビニ
コンビニであれば原則24時間レターパックを購入できます。それでは、委託業務契約によりレターパックを取り扱っているコンビニチェーンとその購入方法をご紹介します。
| コンビニチェーン | 購入方法 | 備考 |
|---|---|---|
| セブンイレブン | 現金、nanaco | 一部店舗のみの取扱い |
| ローソン | 現金 | |
| ファミリーマート | 現金、ファミマTカード、ファミペイ | 一部店舗のみの取扱い |
| ミニストップ | 現金 | |
| デイリーヤマザキ | 現金 | |
| セイコーマート | 現金 |
レターパックの種類と値段
レターパックには、郵便受けに届く「レターパックライト」と、対面で届き受領印が必要な「レターパックプラス」があります。
レターパックライト(青色)
レターパックライトは封筒の青い縁が目印です。料金は送料込みで税込370円、重量が4kg以内、サイズはA4ファイルサイズの荷物まで対応する340mm×248mmとなっています。
厚さの規定が3cm以下と薄いので配達はポスト投函で手軽です。このため、書類や書籍、薄手の衣類などの発送に適しています。ただし、厚みが規定をオーバーしてしまうと、送り主に返送されてしまうので注意しなければなりません。
レターパックプラス(赤色)
レターパックプラスは封筒の赤い縁が目印です。重量が4kg以内、サイズは340mm×248mmまでとレターパックライトと同様ですが、こちらは厚さの制限がありません。また、自宅まで集荷を依頼することも可能です。一方、荷物の厚さによってはポストに投函できないため、配達は対面となります。
「レターパックライト」と「レターパックプラス」の違い
上記のレターパックライトとレターパックプラス、それぞれの違いや特徴を比較すると次の通りとなります。
| レターパックライト | レターパックプラス | |
|---|---|---|
| 封筒 | 青 | 赤 |
| 料金 | 全国一律370円 | 全国一律520円 |
| サイズ | 340mm×248mm | 340mm×248mm |
| 重量 | 4kg以内 | 4kg以内 |
| 厚さ | 3cm以内 | 制限なし |
| 配達 | ポストへ投函 | 対面による受け渡し |
| 集荷 | 不可 | 可 |
レターパックで送れるものは?
レターパックにはサイズや重量が規定内であっても、送れるものと送れないものがあります。
レターパックで送れるもの
まずレターパックで送れるものに関しては、サイズや重量、加えてレターパックライトの場合、厚さについて規定を満たし、封を閉じることができれば、書類や荷物以外に信書でも送れます。
ただし、貴重品や信書については紛失などがあった場合でも補償はされないため注意が必要です。
レターパックで送れないもの
一方、レターパックで送れないものについてはサイズや重量、厚さ以外にさまざまな規定が設けられています。
現金
レターパックでは現金を送ることはできません。紙幣や貨幣いずれも同様です。現金を送りたい場合には、現金書留を利用しましょう。
貴金属類
貴金属類もレターパックでは送れません。これらは現金同様、現金書留であれば送れます。
割れもの
割れものとはガラス製品や陶器などです。レターパックには緩衝材などが備えられていないため、割れやすいものを送るには適しておらず、破損などがあった場合でも補償されません。そのため、壊れものを送る場合には簡易書留や一般書留などを利用したほうがよいでしょう。
壊れもの
精密機器などの壊れものも、割れものと同様の理由でレターパックでは送れません。こちらも、郵送するには簡易書留や一般書留などを利用します。
生もの
冷蔵・冷凍状態での郵送がおこなわれないレターパックでは、生ものを送るのも適しません。
危険物
危険物とは郵便法第12条により禁止されているものです。爆発性や発火性、その他の危険性があるものや毒薬、劇薬、毒物および劇物、病原体またはこれを含んだり付着したりしたものが該当します。
レターパックが発送できる場所や方法
レターパックはレターパックプラスであれば集荷を依頼することも可能ですが、これ以外にどこで発送できるのでしょう。その場所や方法は以下の通りです。
ポスト投函
郵便ポストの間口に入るサイズであればレターパックはポストに投函できます。時間を選ばす、通勤や通学などの合間でも発送可能です。
ただし、レターパックプラスの場合、厚さが3cmを超えると投函できません。
郵便窓口
通常の郵便物と同様、レターパックも郵便窓口で取り扱われています。ポストに投函できない厚さが3cmを超えるレターパックプラスでも、郵便窓口であれば発送可能です。
コンビニ
ローソンなど、店舗の内外に郵便ポストが設置されているコンビニの店舗でもレターパックは発送できます。ただし、こちらも厚さが3cmを超えるレターパックプラスは投函できません。また店舗での預かりも不可です。
集荷
厚さが3cmを超えるレターパックプラスはポストに投函することができないため、郵便窓口の取扱いのほかに、対面による集荷に対応しています。一方、レターパックについては集荷に対応していません。
レターパックの利用方法|送り方の手順
次にレターパックは実際にはどのように発送すればよいのか、具体的にその手順を見ていきましょう。
①レターパックを購入する
レターパックを利用するには専用封筒を入手しましょう。厚みのない荷物や手軽さならレターパック、厚みのあるものや対面での集荷を依頼したいのであればレターパックプラスがよいでしょう。
②必要事項を記入する
レターパックの専用封筒に設けられた、各項目の記入欄には宛名などをもれなく記入します。このとき、品物を記入する欄にはできるだけ具体的な品名を記入したほうがよいこともあります。
これは宛先が遠方で輸送が航空便になるようなケースで、品目のチェックが厳しくなるためです。ただし、個人情報保護などの観点から、各種書類などは「書類」でもかまいません。
③荷物を入れる
サイズを確認し、専用封筒に荷物を入れたら封をします。レターパックには封のためのシールがあらかじめ付属しているので、別途テープなどを用意する必要はありません。
ただし、専用封筒は紙製のため、水濡れが気になる書類などには、あらかじめビニールなどに入れ保護しておくとよいでしょう。また、衝撃が気になる荷物は緩衝材などを同梱するようにします。
④シールをはがす
レターパックには「ご依頼主様保管用シール」が貼られていますが、発送の際には事前にこのシールをはがします。ここに記載された番号は、個々のレターパックの追跡番号で発送後に配達状況を確認するため必要となります。
⑤発送
ここまでの手順が完了したらポスト、郵便窓口、コンビニ、レターパックプラスの場合には集荷のいずれかの方法でレターパックを発送します。
レターパックの注意点
ここからはレターパックを利用するうえで、注意しなければならない点についてみていきましょう。
海外への発送は不可
レターパックは国内のみ発送が可能で、海外へ発送することはできません。海外への発送に対応しているのは、郵便の場合は国際郵便やEMS(国際スピード郵便)などです。
使用済みのレターパックは再利用できない
一度使用されたレターパックの専用封筒は再利用不可です。たとえ同額の切手を貼ったとしても、使いまわすことはできません。そのため、レターパックは発送ごとに新たに購入が必要です。
「ご依頼主様保管用シール」をはがし忘れると追跡サービスが利用できない
レターパックには配達状況を確認できる追跡サービスがありますが、発送の際に「ご依頼主様保管用シール」をはがしていないとサービスを利用することができません。よって、発送の際には必ず「ご依頼主様保管用シール」をはがし、保管するようにします。
配達証をはがしてしまうとレターパックプラスは使えない
レターパックのうち、レターパックプラスには「配達証」のシールが貼られています。「ご依頼主様保管用シール」とは異なり、こちらは発送前にはがしてしまうと発送することができません。ただし、誤ってはがしてしまった場合には、手数料42円で新しい専用封筒と交換できます。
配達日時は指定できない
レターパックはいずれの種類も、配達の日時を指定することはできません。対面による受け渡しされるレターパックプラスについても配達先が不在の場合には郵便受けに不在配達通知書が入ります。この場合には、改めて再配達の日時を指定することになります。
レターパックの利用でよくある疑問と対処方法
注意点以外にも、いざレターパックを使おうと思うと、不明点やわからずに戸惑ってしまうこともあります。そこで、よくある疑問点や対処方法もご紹介します。
レターパックで金券は送れる?
現金を送ることができないレターパックですが、商品券などの金券類はどうでしょうか。結論としては、商品券を含む金券は特に法律で規制されていないため、レターパックでも送ることができます。
郵便において、金券類は信書に該当しないプリペイドカードなどと同様の取り扱いとなるのです。そのため、レターパックでも送ることができるのです。ただし、紛失などがあった場合は信書などと同様、補償がされません。
レターパックで食品は送れる?
レターパックは冷蔵・冷凍状態で食品などの生ものを送れません。しかしながら、常温保存が可能な食品であれば送れます。
ただし、レターパックの専用封筒は紙製で水や衝撃にも弱いため、水気を嫌う食品はビニール袋やジッパー袋に入れる、菓子類など割れやすいものであれば緩衝材で包むなどの工夫をしましょう。
「ご依頼主様保管用シール」をはがし忘れた!どうすればよい?
「ご依頼主様保管用シール」には追跡に必要な情報が記載されていますが、発送先に配達されないわけではありません。とはいえ、「ご依頼主様保管用シール」には発送の控えという役割があります。
そのため、シールをきちんとはがして、荷物が発送先に到着するまで大切に保管する必要があります。
万が一はがし忘れてしまったときには、集荷先の郵便局に投函した場所や時間、差出人の氏名や連絡先などの情報を伝えたうえで問い合わせれば、追跡に必要な情報を得られる可能性もあります。
また、ポスト投函ではなく郵便窓口であれば、「ご依頼主様保管用シール」をはがし忘れていても郵便局員が気づいて、台紙に貼って手渡してくれることもあるので安心です。
宛名を書き損じてしまった!発送はできる?
レターパックは宛名や住所を書き損じても、レターパックプラスの「配達証」のシールを誤ってはがしてしまったときと同様、手数料42円で新しい専用封筒と交換できます。また、専用用封筒を破損してしまった、濡らしてしまった、といった場合でも同様に交換が可能です。
レターパックの専用封筒は折り曲げたりしてもよい?
レターパックの専用封筒は折り曲げたり、ガムテープや粘着テープで補強しても問題ありません。また、厚さに制限のないレターパックプラスであれば、箱型に加工するなどして、より厚みのあるものを入れることも可能です。
ただし、加工や補強や加工をする場合には表面の「料額印面」が隠れないようにしましょう。封筒が著しく破れていたりすると発送できないので注意してください。
レターパックの配達日数はどれくらい?
レターパックの配達日数は発送先によって異なりますが、おおよそレターパックライトで普通郵便と同等の日数、レターパックプラスは速達並みです。
ただし基本的には到着までのスピードに違いはないとされ、原則、大半の地域で翌日から翌々日には配達されます。
また土曜日・日曜日・祝日も配達がおこなわれているレターパックは通常の郵便物よりも到着が速いことがあります。
ポスト投函の際、レターパックは左右どちら?
郵便ポストのなかには投函口が左右2つに分かれているものがありますが、これは「手紙やはがき類」と「その他の郵便物」に区別されています。
レターパックは「その他の郵便物」に投函してください。投函口が1つしかないポストに関しては、手紙やはがきと一緒に投函してもかまいません。
レターパックは宅配ボックスに配達してもらえる?
近年、自宅の玄関先などに宅配ボックスが設置されるケースが増加していますが、対面による受け渡しが原則となるレターパックプラスについては、宅配ボックスへの配達は不可です。
またレターパックライトについても、宅配ボックスに入らない場合には不在配達通知書が入り、持ち戻りになります。基本的にレターパックは宅配ボックスへの配達はおこなわれていないと考えたほうがよいでしょう。
宛名・差出人はシールでもOK?
フリマアプリやオークションサイトの利用などにおいてレターパックをまとめて大量に発送したい場合、それぞれ宛名や差出人を記入するのは大変です。
そんなときは、宛名・差出人ともに住所や名前を記入する枠内に貼ればシールを使用できます。レターパックはラベルメーカーなどを利用し、作成したシールを添付して発送できます。
まとめ
レターパックは全国一律料金で、荷物の種類や発送する場所によっては、宅配便などよりもリーズナブルに利用できます。
またポスト投函やコンビニの店舗からの発送、集荷にも対応するなど利便性の高さが魅力的です。
お忙しい方やお急ぎで発送したい方は、ぜひポストやコンビニで利用できるレターパックを上手に活用してみましょう。