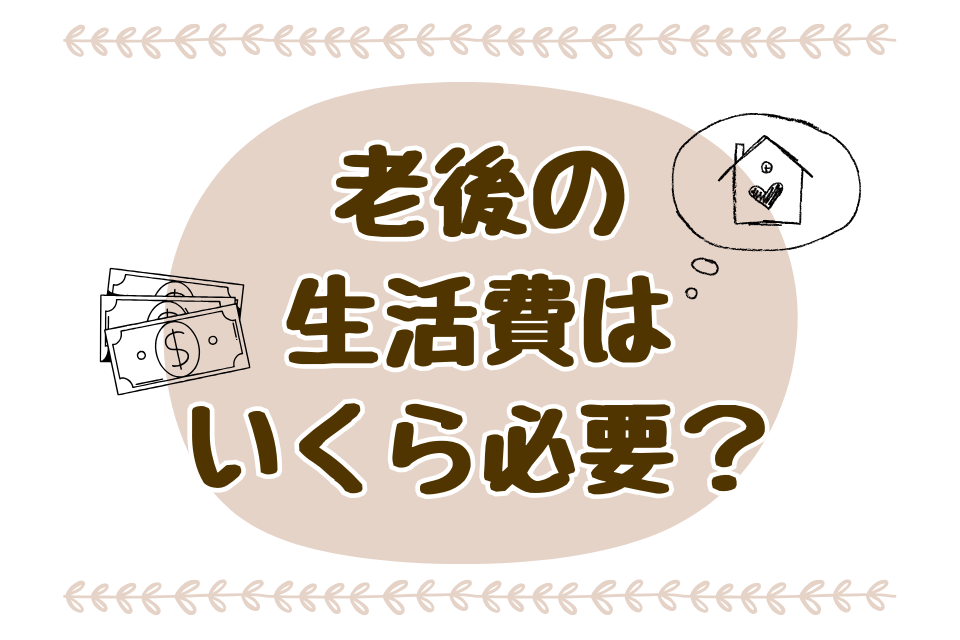しかし、現役で働いている間は老後の生活費まで考えるのは、難しい人もいるでしょう。

「老後の生活費では何が一番お金がかかる?」

「貯蓄や投資のために今からできる稼ぎ方は?」
この記事では、老後の生活費について、必要な金額や将来に向けたお金の貯め方などをまとめました。
今のうちに老後を見越した貯金をしたい人は、参考にしてください。
老後の生活費はいくら必要?

老後は仕事を退職するため、それまでの貯金や投資から生活費を賄う必要があります。
老後の生活費について、2024年時点の現状や、今後の見通しを紹介します。
不安な将来の老後の生活費
老後の生活費は住んでいる人数や場所によって、必要な金額が変わってきます。
身体的な衰えから食事量が減る一方で、通院で使う金額が増えるなど、老後特有の理由で変化する可能性もあります。
【一人暮らし】老後の生活費はどれくらい必要?
老後に一人暮らしをしている場合、1ヶ月あたりの生活費では以下の金額がかかると想定されます。
- 食料:約37,000円
- 住居:約12,000円
- 光熱・水道:約14,000円
- 家具・家事用品:約6,000円
- 被服及び履物:約3,000円
- 保険医療:約8,000円
- 交通・通信:約14,000円
- 教養娯楽:約14,000円
- その他の消費支出(雑費・交際費など):約31,000円
- 直接税(所得税や住民税など):約6,600円
- 社会保険料(健康保険や介護保険など):約5,600円
直接税や社会保険料といった必ず支払う必要があるお金を除くと、15万円前後の支出になります。
上記は平均的な金額であるため、より豊かな生活を送りたい場合は追加で10万円は必要になるでしょう。
【夫婦二人暮らし】老後の生活費はどれくらい必要?
老後に夫婦二人暮らしをしている場合、1ヶ月あたりの生活費では以下の金額がかかると想定されます。
- 食料:約67,000円
- 住居:約15,000円
- 光熱・水道:約22,000円
- 家具・家事用品:約10,000円
- 被服及び履き物:約5,000円
- 保健医療:約15,000円
- 交通・通信:約29,000円
- 教養娯楽:約21,000円
- その他の消費支出:約20,0000円
- 交際費:約22,000円
- 仕送り金:約1,300円
- 直接税(所得税や住民税など):約13,000円
- 社会保険料(健康保険や介護保険など):約19,000円
必ず支払う必要があるお金を除くと、一人暮らしと比較して約1.5倍の23万円前後の支出が必要になります。
家庭によっては保険医療や娯楽など、一人あたりに必要な費用が2倍以上かかる可能性もあります。
持ち家かどうかや?病院にかかる回数などで必要な費用も変わる
上記の生活費は、個人の生活環境によって必要な費用が大幅に変動します。
生活環境の例としては、以下のような住宅や医療にかかわる項目が該当します。
- 賃貸契約費:10万円前後 ※お住まいによって変動あり
- 持ち家のリフォーム費:約280万円
- 入院時自己負担費:1回の入院あたり約20万円
- 介護費用:月あたり約8万円
- 葬儀・墓:それぞれ10万円以上は必須 ※家族葬や永代供養などの形式によって変動あり
年齢を重ねると足腰の弱りから、バリアフリー化のためのリフォームや賃貸の変更が必要な人もいるでしょう。
入院時の自己負担は入院する日数によって変動していて、年齢が高くなるほど病気を患ったときの入院日数は長くなる傾向があります。
老後は病気にかかる回数が増えやすいため、通院や薬代と合わせて医療や介護の費用は膨れ上がる可能性があります。
将来に向けて変わってくるもの
先に紹介した老後の生活費は、2024年時点の生活環境や保険制度、物価から想定された金額です。
現役の人が年齢を重ねた頃には、自身の生活様式や物価などが大きく変わる可能性も十分考えられます。
医療制度や生活スタイルが変わる恐れもある
2024年時点の医療費の自己負担は、
- 75歳以上が1割
- 75歳以上かつ現役並み所得者は3割
上記の設定です。
しかし、将来的に医療制度が変更された場合、自身が75歳上になったときの自己負担が多くなる可能性も考えられます。
自身が病気や事故に遭った場合、生活スタイルの大幅な変更から、今以上の医療費が必要になるケースもあります。
今後もますます生活費や必要な老後費用が上がる可能性がある
2024年時点でも生活に必要な用品の物価は、世界情勢の変動や原材料の高騰の影響から日々値上がりしています。
将来的にも大幅な値下がりが発生するとは考えにくいため、今以上に老後の費用は必要になる可能性が高いと思っておいた方がよいでしょう。
老後に受け取れるお金はいくら?

老後の生活費に充てられるお金として、現在納めている金額から将来的に支給される年金があります。
しかし、働き方や収入状況からもらえる金額が異なるため、人によっては別口で将来的にお金を引き出せる準備が必要です。
老後に受け取れる年金について、おおよその金額や今後の見通しを確認していきましょう。
老後に受け取れる金額はいくら?
老後に受け取れるお金は、国民年金と厚生年金を合わせて月額約14万円です。
共働きの夫婦の場合は、単純計算で2倍の月額約28万円もらえますが、年金の内訳は人によって大きく異なっています。
さらに、個人で加入している保険や退職金の有無によっては、月あたりでもらえる金額はもう少し増える可能性があります。
国民年金(老齢基礎年金)
国民年金は、20歳以上60歳未満のすべての日本国民に加入義務がある年金です。
60歳以降にもらえる年金は、年金制度の基礎部分を担う点から、「老齢基礎年金」と言われています。
現役のときには毎月、もしくは数ヶ月分をまとめて納付をしていき、納付額によって受給額が変わってきます。
国民年金の平均受給額は、月額約56,000円です。
年金の受給は60歳から75歳まで選択できて、受給を遅らせると1回あたりの受給額を増やせます。
厚生年金(老齢厚生年金)
厚生年金は、会社員などの働いている人が加入する年金です。
60歳以降にもらえる年金は、「老齢厚生年金」と言われていて、国民年金に上乗せする形で支給されます。
現役のときの収入から毎月、ないし一定期間で納付分が差し引かれるため、年収によって将来的な支給額が変わってきます。
一般的な会社員が加入した厚生年金の平均受給額は、月額約9万円です。
そのほか個人で入っている私的年金や退職金など
上記の年金は国が用意した年金制度ですが、そのほかにも保険会社等が取り扱う私的年金に加入していた場合は、毎月の受給が発生します。
勤務先によっては退職金制度を一括支給ではなく、年金形式で毎月支給してもらえるケースもあります。
年金制度以外の支給額は、納付額や勤務先への貢献度で変動するため、明確な金額は提示できません。
しかし、長期間の納付や数十年単位で勤務している場合は、毎月の支給額に期待してもよいでしょう。
年金制度が変化する可能性はある
生活費が将来的に変化する可能性があるように、年金制度も生活環境や情勢の変化から現在とは異なる形式になる可能性があります。
そのため、国民年金や厚生年金だけをあてにするのは危険です。
年金制度は賦課式なので、少子高齢化が進むことで保てない可能性
現在の年金制度は、現役世代が納めた保険料を、その世代の高齢者の受給額にあてる賦課方式を採用しています。
しかし、少子高齢化で若い働き手が減った場合、将来的に受給する側の多さに対応できない可能性があります。
制度が完全に崩壊するわけではありませんが、対応できなくなったときは受給額の減少は避けられません。
受取年齢の変化や受取額が変化する可能性
現在の年金の受給開始年齢は、原則65歳です。
以前は国民年金が65歳、厚生年金が60歳からでしたが、2013年度から厚生年金の受給開始年齢が段階的に引き上げられました。
2013年度の受取年齢の引き上げは、2000年の法律改正で決められました。
そのため、現在年金を納めている人の受取年齢が変化する可能性は、低いと言えます。
受取額についても、現在納めている金額を参照して支給されるため、将来的な受取額が急に変更される可能性は低くなっています。
しかし、変化する可能性が全くないとは言えないので、別の備えが必要です。
将来的の受取は変わらなくても、保険料が高額になる可能性
現役世代の将来的な受取額が変わらない場合でも、健康保険や介護保険などの保険料が高くなると、老後の負担は増えてしまいます。
医療保険制度を維持するために、今後も保険料が上がる可能性は十分考えられるため、ほかの制度の変更にも目を向ける必要があります。
3号が廃止される可能性
第3号被保険者とは、厚生年金の加入者に扶養されていて、年収が130万円未満の人であり、原則として保険料を納める必要がありません。
しかし、近年は共働き世帯が増えており、3号の必要性が議論されている状態です。
3号が廃止された場合、扶養者も保険料を納める必要が出て、納めた金額によって、もらえる年金額が決まる可能性が出てきます。
老後不安を解消するために、今できること

老後の生活費や年金制度に不安を感じている人は、今のうちに老後で使うお金を用意しておくのがおすすめです。
単に貯金を増やすのも悪くありませんが、現在はさまざまな方法で貯蓄を増やせます。
今からできる老後の生活費の増やし方について、確認していきましょう。
1.【貯金する】貯金の方法
老後の生活費を単純に増やす方法としては、貯金が真っ先に思い浮かぶ人も多いでしょう。
しかし、現在の生活費やストレス解消の娯楽にもお金が必要な点から、思うように貯金が貯まらない場合があります。
老後に備えて本格的に貯金をする場合は、以下の方法からご自身に合うものを実践してみましょう。
貯金用口座を作ったり、銀行の自動積立を利用する
貯金できない人に有効な方法として、普段の生活費や引き落とし用の口座とは別に貯金用の口座を作る手段があります。
ご自身が入金以外で触れない口座があれば、1つの口座で金銭的に余裕があると思って使い過ぎてしまうのを防げます。
「複数の口座を作るのが手間だ」と感じる人は、銀行が用意する自動積立を利用するのもよいでしょう。
自動積立はご自身で指定した金額を、毎月自動的に口座から銀行の定期預金として預け入れられます。
積み立てたお金は途中でも引き出せるサービスが多いため、自分のペースで無理なく貯蓄を増やせます。
別口座を作っても預け忘れそうだと思う人は、自身の銀行口座が自動積立に対応しているか、確認してください。
私的年金保険などの貯蓄型保険に入る
「お金を預けるだけでは金利が低くてもったいない気がする…」と感じる人は、以下のような貯蓄型保険への加入がおすすめです。
- 私的年金保険(厚生年金基金、国民年金基金など)
- 終身保険(低解約返戻金型終身保険)
- 養老保険
- 個人年金保険
上記の保険では、保険料を積み立てて、納付期間の満期保険料や解約返戻金を受け取れます。
可能であれば、
- 一括払い後に据え置きで増える商品
- 積立金額を早期に払い済みにすることで増額される商品
などを探し、高利率を狙うのがおすすめです。
ただし、積立期間中にお金を受け取ったり、期間満了前に解約した場合は、満期や解約時の支給額は減少します。
保険商品は保険期間や支払い期間が決まっているため、「毎月確実に支払える金額であること」が非常に大事な商品です。
万が一に備える保険であるため、将来的な受け取りだけでなく、保険内容も重視しましょう。
NISAやiDeCoを利用する
銀行口座の貯金を運用する方法として、NISAやiDeCoは候補になります。
どちらも運用したお金が非課税になるため、高額なお金を得ても税金を差し引かれません。
2018年からは積立型のつみたてNISAが新たに登場して、現在のNISAでは積立型は主流になり始めています。
初心者でも運用しやすいサービスが増えているため、個人で株式を運用するのが難しい人は検討してもよいでしょう。
貯金するには「支出を減らす」または「稼ぎを増やす」
自動積立や保険加入などを含めた貯金は、現在の生活費を差し引いたうえで預けるお金を捻出しなければいけません。
お金を捻出する方法としては、
- 現状の支出を減らす
- 稼ぎを増やす
いずれかの2択になります。
しかし、貯金のために無理をして支出を減らすと、現在の生活や健康に影響を与える可能性があります。
そのため、無理のない範囲で支出を少し減らしながら、より稼ぎを増やせる方法を探っていくのがおすすめです。
2.【稼ぐ】お金を稼ぐ方法
現在の生活や貯金のためにお金を稼ぐ方法も、いくつか候補があります。
しかし、今すぐに稼ぎを増やせるのは小規模で始める副業に限られています。
昇進・転職する
仕事でよりお金を稼ぐためには、現在の職場で昇進するか、別の職場へ転職する手段が考えられます。
昇進や、より給料が高い職場で勤務できれば、収入が増えて年金の納付額も増やせます。
しかし、昇進や転職は必ずしも成功するとは限りません。
評価を上げたり、勤務環境が変わったりする関係から、現在よりも仕事量が増えて、心身に影響が出る可能性もあります。
現状の給料に対して不満がある場合は実践してもよいですが、貯金のためだけに実践するのは推奨しづらい方法です。
投資する
現在の仕事は継続しつつ、お金を稼ぐためには株式などに投資する方法が考えられます。
成功すれば株式のみで稼げるケースもありますが、一方で変動により大きく損をするリスクもあります。
投資先に価値が出始めるまで一定の時間がかかるため、十分な稼ぎにつなげるためには長期的な運用を考えなければいけません。
投資家に依頼する場合でも現在はつみたてNISAなどの存在から、サービスに任せた方がよいケースもあります。
専門知識を十分学んだうえで、自らお金を運用したい人は候補にしてみましょう。
副業する
現在就いている職業で問題なければ、副業を始めると純粋に稼ぎを増やせます。
副業といっても、しっかり勤務する必要はなく、短期バイトや個人取引など短時間や小規模で始められるのが強みです。
個人で販売ルートや顧客を開拓できれば、本業と同等の稼ぎも期待できます。
今すぐ稼ぐという点を重視したい人は、職場の規則を確認して副業を始めてみましょう。
3.政治に興味を持つ
直接的にお金が増えるわけではありませんが、政治に興味を持つのも今すぐできる行動の1つです。
将来的な法改正や受給額は、少なからず政治家の判断によって左右されます。
政治に興味を持って、現在の若者がよく過ごせるような考えを持つ人に投票すれば、今後の制度をよい方向に変えられる可能性があります。
ある意味では、無料で行える先行投資になるため、全く関心がなかった人は、政治や選挙に興味を向けてみましょう。
老後不安解消のために、まずは稼ごう!

現在の生活や将来的な貯金のために、本業に加えて副業を始めるのは有効な方法です。
老後の不安解消につながる副業による稼ぎ方について、確認していきましょう。
今より稼ぎたいなら、副業を始めよう!
現在の仕事からさらに稼ぎを増やす場合、以下の点から副業が最も早くお金を増やせます。
- 転職・昇進:確実性がなく、結果が出るまで時間がかかる
- 貯金・投資:使うお金を現在の収入から捻出する必要がある
- 副業:仕事量は増えるが、休日や隙間時間の活用でお金は確実に増える
貯金や投資をしたい人も、これからの生活で使うお金を確保するために、副業でさらに稼ぎを増やしてみましょう。
最もおすすめな副業は「物販」の仕事!
副業には複数の選択肢がありますが、最もおすすめなのは物販です。
物品をネット販売する副業であり、近年では以下のようなサイトが主な販売先になります。
- フリマアプリやオークションなどで不用品やレア商品を出品する
- 正規の販売元や海外ECサイトから商品を仕入れて販売サイトに売り出す
始めるときに複雑な契約をしたくない場合は、個人販売のまま継続できます。
一方、正規の契約を結んで法人販売にした場合、ECモールへ出店して本格的に売り出せます。
物販は今後も成長性のある副業として注目されている
物販市場は近年のネット販売環境の充実や、海外との取引から、今後も成長性がある副業として注目されています。
将来的にも、継続して販売できる点を考えると、老後の収入先としても期待できます。
世界中をターゲットに商売ができる!
物販は販売先をしっかりと選んだ場合、世界中に向けて商品を販売できます。
国内でも主要な販売サイトであるAmazonは、出品者側になると多くの国での出品が可能です。
国内外に購入者がいれば、さまざまな商品が売れやすくなります。
まだライバルが少ないので、稼ぐための土台作りができる!
物販は副業として注目されていますが、現状の参入者は多いわけではありません。
そのため、ライバルが少ないうちに参入しておけば、将来的に稼ぐための土台作りができます。
新規参入者が来ても継続的に稼げるように、今のうちの参入がおすすめです。
初期投資も少なく、初心者でも参入しやすい
物販は小規模から始める場合、初期投資が少なく、初心者でもすぐに始められます。
具体的な初期費用としては、
- 商品の仕入れ費用
- 出品先の利用料
- 購入されたときの送料
- 商品を保管する場所代や電気代
などが挙げられますが、サイトによっては出品先の利用料はかかりません。
商品の仕入れについても、少量の仕入れで調整すれば、費用を抑えられます。
コツをつかめば大きく稼ぐことも可能!
物販は販売方法や仕入れのコツをつかんだ場合、お得な仕入れや価格設定から大きく稼げる可能性があります。
仕入れや売り出しが安定すれば、必要な作業を少なくできるため、本業への負担を軽減しながら副業を続けられます。
物販の仕事を始める方法
副業として物販を始める場合、売りたい商品や販売先を選ぶ必要があります。
販売するまでは簡単に行える一方で、ある程度稼げたときは確定申告を気にする必要も出てくるため、事前に流れを覚えておきましょう。
物販業務の流れ
物販を開始するまでの主な流れは、以下のとおりです。
- 売りたい商品の決定
- 商品の市場調査
- 販売先と仕入れ先の選定
- 仕入れ先への発送と商品受け取り
- 商品を販売先に出品
- 購入後の発送
売りたい商品のジャンルや販売先は、一度決めれば省略できますが、そのほかの作業は毎回の流れで必須になります。
まずは気軽に出品から始めてみよう!
販売サイトへの出品は、初めてやると尻込みするかもしれませんが、気軽に行ってみましょう。
市場調査をしっかり行ったうえで商品を出品すれば、初めは少ない人数でも十分売れる可能性はあります。
商品を出品しない限りは、購入者に見てもらう機会を作れないため、積極的に出品するのが推奨されます。
本格的に仕入れる前に物販の雰囲気を練習したい場合は、フリマアプリやオークションサイトを利用するのもおすすめです。
手軽に商品の個人販売が行えるアプリやサイトであり、出品する流れは物販とほとんど同じになります。
まずはフリマアプリやオークションサイトなどで商品の売買をして練習してみるのもおすすめです。
売り上げが20万円を超えたら確定申告をする必要があるので注意
物販に限らず、副業の稼ぎが20万円を超えた場合、収入に対して確定申告を行う必要があります。
確定申告は該当者自身で行う場合、税務署やe-Taxのホームページから、必要書類の入手や手続きができます。
物販を始める際、個人事業主として開業届を出している場合は、申告時に青色申告を選択可能です。
青色申告をすると事業主になるため、確定申告は必須となりますが、
- 特別控除の対象となる
- 経費による納税額の差し引き
など、事業所得にすることで、納付する税金を少し減らせるメリットが存在します。
物販の業務が安定してきて20万円以上の収入が当たり前になったときは、開業届を出して青色申告を受けられるようにするのもよいでしょう。
ただし、副業がNGな会社の場合は、会社の規定により事業主になれない場合もありますので、ご注意ください。
一方で、副業の稼ぎが20万円以下の場合、基本的に確定申告の義務は発生しません。
ご自身の稼ぎが確定申告に該当しているかを判断できない場合は、税務署へ行って相談するのがおすすめです。
物販では市場調査の重要性が高い
物販の流れでは、商品の仕入れや価格設定も気にする必要はありますが、それらの基準を決める市場調査は重要性が高い項目です。
市場調査をせずに商品の仕入れや販売を行ってしまうと、
- 仕入れたタイミングで売れない商品を大量に仕入れてしまう
- 市場価格に合わない価格設定にして売れ残る、もしくは利益で損をする
- 同じ商品を出品するライバルの多さから、価格競争に巻き込まれる
というように、失敗や売上の損失につながります。
物販の仕事を始めるならオークファンがおすすめ!

市場調査は販売先以外の販売サイトの状況も調査するのが基本であり、複数のサイトの情報を総合して、販売時期や価格を決めます。
しかし、販売サイトを1つずつ閲覧して情報収集するのは効率が悪く、副業の難易度を上げてしまいます。
そんなときに活用したいのが、リサーチツールのオークファンです。
無料会員で商品の価格相場が一括検索できる!
オークファンでは、以下の販売サイトについて、商品ページや価格相場を一括で検索できます。
国内の主要販売サイトが揃っており、プランによっては海外のサイトもリサーチ対象に含められます。
オークファンのプランは、以下のように4段階に分かれています。
| 無料一般会員 | ライト | プレミアム | プロPlus | |
|---|---|---|---|---|
| 月額 | 無料 | 1,100円 | 2,200円初月無料 | 11,000円 |
| 広告 | あり | なし | なし | なし |
| 落札相場検索 | 6か月間 | 過去10年分 | 過去10年分 | 過去10年分 |
| 期間おまとめ検索 | 月3回 | 月100回 | 月1200回 | 無制限 |
| Amazon検索機能 | 制限あり | 制限あり | 無制限 | 無制限かつSEO補助ツールあり |
| マイブックマーク | 30件まで | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
一般会員は検索範囲や登録件数に制限はあるものの、リサーチ対象のサイトへの検索は無料で行えます。
仕入れた時期に人気や流行の商品であれば、無料分の過去6ヶ月の落札相場検索でも十分な情報が収集できるでしょう。
一方で、本格的な物販や価格変動幅を長期的に見るべき商品については、プレミアムやプロPlusへの登録がおすすめです。
ライト版でも一部の機能は解放されますが、あくまでプレミアムを簡易的に体験するプランになっています。
プレミアムは売買の両方に強く、プロPlusは販売のみに特化したプランであるため、自分の物販スタイルに合う方を選んでください。
副業物販のためのセミナーも豊富!

オークファンでは、副業物販に関連するセミナーを定期的に無料で開催しています。
初心者向けや現在の物販事情についてわかる内容が多く、そのほかにも豊富なラインナップのセミナーを用意しています。
セミナーへの参加を希望する場合は、サイト登録とは別にオークファンの公式LINEを友だちに追加しましょう。
まとめ
老後の生活費について、必要な金額や将来に向けたお金の貯め方をまとめると、以下のようになります。
- 老後の一人暮らしは月額約15万円、夫婦二人暮らしは月額約23万円の生活費が必要であり、より豊かな生活を望む場合は追加で10万円は必要
- 老後に受け取れる年金は月額約14万円で、保険料の納付額や収入の差によって金額は変わる
- 生活費に必要な金額や年金制度、支給額は将来的に変わる可能性がある
- 貯金は銀行の自動積立や貯蓄型保険への加入、NISAやiDeCoといった資金運用といった選択肢がある
- 貯金するために稼ぐ手段として、昇進や転職、株式などへの投資は確実ではなくやや時間がかかる
- 副業は仕事量が増えるものの、お金は確実に増やせる点で稼ぐ際の有力候補となる
- 物販は注目の副業であり、初心者の始めやすさや初期投資の少なさ、大きな稼ぎが期待できる
- 物販の市場調査や副業としてのやり方に悩んだときは、オークファンのツール利用や無料のセミナー参加がおすすめ
今すぐに老後の備えをしたい人は、物販を副業として始めておくと、貯金や資金運用に使えるお金を用意できます。
早く行動するほど、将来的に十分な備えを達成できるため、自分に合う老後の生活費の確保を実践してみてください。