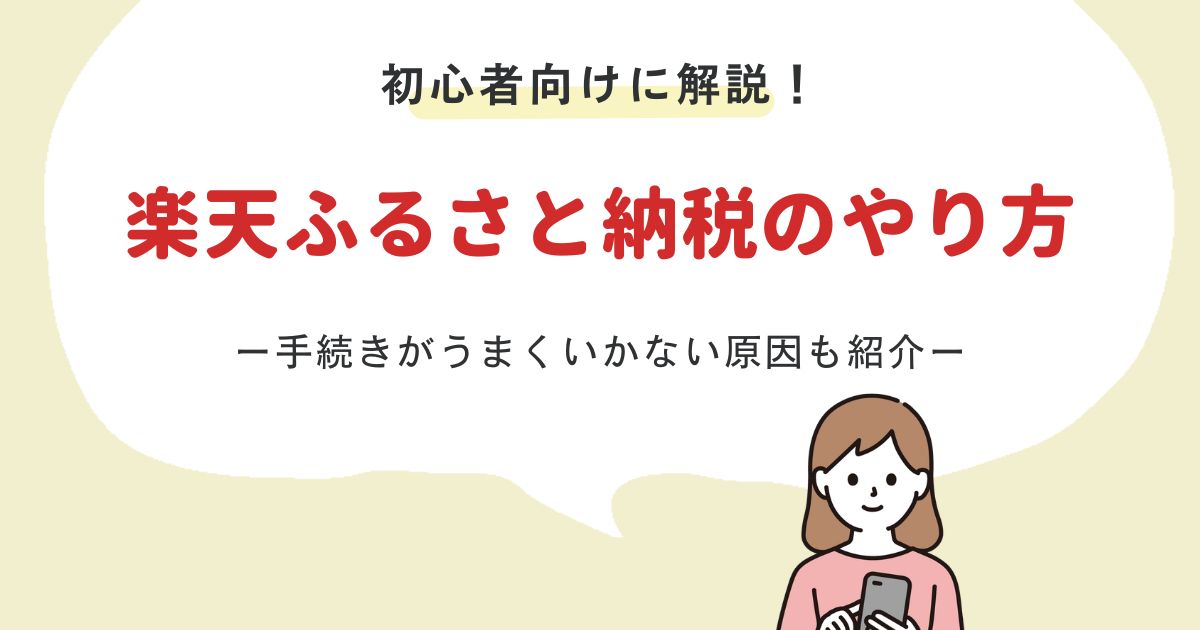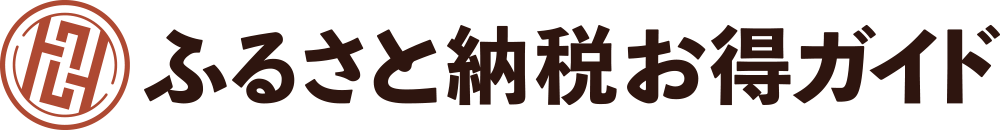2008年に始まったふるさと納税は、徐々に知名度が高まり年々利用者が増えています。
しかし・・・
ふるさと納税をしたら確定申告が必要なの?
会社員がふるさと納税をしたら、年末調整がめんどくさいのでは?
といったお悩みを抱えている方もいるのではないでしょうか?
ふるさと納税だけならば、実は確定申告もそれほど難しくありません。
しかもワンストップ特例申請が使えれば、もっと簡単に控除申請ができます。

確定申告期間は冬!
さむーい中わざわざ税務署に行くなんて嫌ですよね。
しかも国税庁のラインで入場整理券の「予約」をして行っても申告会場で待たされてしまうものなんです。
記事の前半ではお家にいながらできる確定申告について解説しますが、記事の後半ではさらに簡単なワンストップ特例申請もご紹介します。
ぜひあなたにあったやり方で、今年はおうちから快適にふるさと納税の控除申請をしましょう!
本サイトには広告が含まれますが、皆さまに役立つ情報を厳選の上掲載しております。
確定申告とは?ふるさと納税で控除申請する方法は2つ


確定申告とは、1年間の所得(売上から経費を引いた残り分)に対して税金を計算し、国(税務署)に納めるべき税額を報告する手続きのことです。
ふるさと納税で寄付した分を所得から差し引くためには、控除申請しなくてはなりません。



この控除申請をすることで、寄付金額が控除・還付され、実質2,000円の自己負担だけで返礼品がもらえてお得になるんです。
ふるさと納税で控除申請する方法は、従来からの確定申告と手続きが簡単になったワンストップ特例申請の2つがあります。
ふるさと納税をする上で押さえておくべきポイント
会社員はワンストップ特例申請でOK
会社員は基本的にワンストップ特例申請が可能です。
そもそもワンストップ特例申請自体が、会社員が「簡単に」できるように作られた制度だからです。
確定申告が不要になるワンストップ特例を利用すれば簡単に控除申請ができます。



簡単なワンストップ特例申請の方法をこちらから確認してください。
ふるさと納税の申請期間は?
ふるさと納税にる寄付金額の控除をうけるためには、申請期間に手続きを完了しなくてはなりません。
ワンストップ申請をする場合は、寄付した翌年の1月10日までです。
たとえば2023年中に寄付した場合は、2024年1月10日までにワンストップ特例申請書を寄付した自治体に郵送します。
ワンストップ特例申請の申請期間を過ぎてしまった場合は確定申告をする必要があります。
確定申告は、原則毎年2月16日~3月15日までの1か月間が、土日や祝日と重なるとずれる場合もあります。詳しい日程は、確定申告特集で確認できます。



ふるさと納税でいつまで寄付できるのかも知っておくといいですよ!
副業は住民税の金額で会社にバレる可能性がある
会社員の場合、住民税決定通知書から会社に副業をしていることがバレてしまう可能性があるので要注意です。
副業をすると収入が増えるので住民税が高くなります。
住民税とは?
住民税とは、住んでいる自治体に支払う税金のことで、定額負担の均等割りと所得金額に応じた所得割を合算し計算するため、1年間の収入に応じて変わります。
もちろんふるさと納税をすれば住民税が減るので、それも会社側は分かります。



ふるさと納税をお得に利用しようとするほど、副業がバレる可能性も高くなりますので、ふるさと納税のメリットと、副業がバレるリスクを同時に考えましょう。
住民税決定通知書の例をみてみる
ふるさと納税で確定申告が必要なパターン4つ
ふるさと納税をするならば、断然ワンストップ特例申請が手続きが簡単なのでおすすめです。
しかし「確定申告」を必ずしなくてはならない場合もあるのです。
確定申告が必要なパターン4つ
4つのパターンにあてはまる場合は、ワンストップ特例制度ではなく、確定申告で控除の申請をしましょう。



あなたが確定申告が必要なのかを、パターン別に確認していきましょう。
1.もともと確定申告が必要


もともと確定申告が必要な人は、大きく2つに分けられます。
- 自営業やアパート経営などの不動産収入がある人
- 会社員や公務員だが年末調整だけでは正しく納税額が把握できないため、確定申告が必要となる人
②についてですが、そもそも会社員のような給与所得者は会社で年末調整をおこなうため、本来確定申告は必要ありません。
しかし以下にあてはまる会社員は、会社の把握しきれない収入があったり、収入により税率がことなるため確定申告が必要になります。
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
- 2か所の会社から給与を受けている人
- 給与以外の副収入の所得合計額副業で20万円を超える人
確定申告をしないと、税金が適正に計算されなくなり、余計に納めすぎて損することもでてきたりもします。(またその逆の場合もあります。)
2.住宅ローン控除や医療費控除を受ける


住宅ローン控除(初年度)や医療費控除を受ける場合にも、確定申告が必要です。
そのため住宅ローン控除や医療費控除をうける場合には、ワンストップ特例申請は使えないことになります。
医療費控除とは? 住宅ローン控除とは?
医療費控除は、ある一定額の医療費を払った場合に、医療費控除額に応じて所得が控除されます。
住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して住居を購入した場合に、年末時点の住宅ローンの残高に応じて所得税や住民税から控除されます。
(一定の要件があり。)
ただし住宅ローン控除が2年目以降は、会社の年末調整で処理されるため、確定申告をする必要はありません。



医療費控除や住宅ローン控除(初年度のみ)があると必然的に確定申告になってしまいます。
医療費控除の仕方や住宅ローン控除の仕方についての国税庁の動画チャンネルもあるので参考にしてみてくださいね。
3.6つ以上の自治体に寄付した


ふるさと納税で6つ以上の自治体に寄付した場合も確定申告が必要です。ワンストップ特例制度を利用するには、以下の要件を満たす必要があるからです。
- 確定申告が不要な給与所得者
- ふるさと納税の自治体数が5自治体以内
- ふるさと納税先の自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出
ふるさと納税で6つ以上の自治体へ寄付した場合には、2の要件から外れてしまいます。
ただし同じ自治体であれば、複数回寄付しても1自治体としてカウントされます。
ワンストップ特例の活用例をみる





ワンストップ特例制度は、上手に使えば5自治体だけという制限があっても、色々な返礼品を返礼品をもらえるんです!
4.ワンストップ特例の申請期間が過ぎた


ワンストップ特例制度の申請期間を過ぎてしまった場合、確定申告が必要となります。
ワンストップから確定申告に変更する際に特別の手続きは必要ありません。
確定申告期間になったら、寄付したすべての自治体の「寄附金のわかる証明書」を準備して確定申告をしましょう。
最終的には確定申告でした内容で、住民税の控除・還付がされます。



ワンストップはあくまでも確定申告の簡易版です。
つまりワンストップ特例<確定申告なのです。
もし寄付した当初ワンストップ特例申請を考えていたけれども、医療費控除で確定申告が必要になってしまった場合もあると思います。
その時は確定申告ですべての寄付を申告しましょう。
ふるさと納税後の確定申告のやり方
ふるさと納税をした後の確定申告は、①税務署(確定申告会場)での手続きと②e-TAXの手続きの2つです。



ここではお家にいながらできるe-Taxを使った方法を解説していきます。
【ポイント!】ふるさと納税後の確定申告のやり方
確定申告に必要な書類等一覧
確定申告に必要な書類は、以下の通りです。
- 寄付金額がわかる証明書(寄附金額受領証明書または寄附金控除に関する証明書)
- 源泉徴収票
- 還付金受け取り用口座番号
- マイナンバーカード
- マイナポータルアプリをダウンロードしたスマホ
※マイナンバーカードがない場合は、ID・パスワード方式できますが事前に税務署にて手続きが必要です。
所得控除の情報を入力する


ふるさと納税で確定申告の際には、寄付した金額分の所得を差し引いて計算するため、「所得控除の情報」を入力する必要があります。



ここでは確定申告の最初の画面から説明していきますが、所得控除の入力方法から知りたい方はstep4からみてください!


「国税庁 確定申告等作成コーナー」にアクセスし、「作成開始」をクリックしましょう。
次に税務署の提出方法を選択します。



マイナンバーをもっているならば、スマホを使ってのe-Taxが一番お手軽ですよ!
どんな提出方法があるのか見てみる
①スマホを利用でe-Tax
②ICカードリーダーえお利用してe-Tax ☚特別な機器が必要!
③ID・パスワード方式でe-Tax ☚事前に税務署で手続きが必要!
④印刷して、郵送か持参
⑤税理士に依頼




「令和5年分の申告書の作成」→「所得税」の順にをクリックしましょう。
マイナポータルと連携することで、証明書データを自動で取得して申告書を作成できます。


源泉徴収票をみながら入力しましょう。
副業で他に収入がある、他の所得がある場合も、この時点で入力していきます。



一年間の得た所得をすべて合算するのです!


ふるさと納税は、「寄附金控除」の右側にある「入力する」をクリックして入力していきます。
なお医療費控除がある場合も、この画面から入力します。


まず「寄附先等から交付された証明書等の入力」画面で①の「入力する」をクリックします。


①「寄附金の種類」は「都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税など)」を選択
②寄付年月日の入力
③都道府県か市町村かの選択
④寄付した自治体をリストボックスから選ぶ →自動的に、所在地と名称が入力されます。
⑤寄付金額の入力
すべての入力が完了したら、「入力内容の確認」をクリックします。


誤りがあるようならば、「訂正」をクリックして入力し直しましょう。


入力された金額を基に計算した寄付金控除額が表示されるので、金額に間違いがなければ「OK」をクリックします。


「所得控除の入力」画面で「入力内容から計算した控除額」を確認し、間違いがなければ入力完了です。
次の画面に進むと、所得税から還付される額が表示されます。
「住民税等に関する事項で」の画面で必要事項をチェックし、住所・氏名や振込口座番号を入力していきます。



後日、振込口座に還付金が振り込まれますので、楽しみにまっていましょう。
寄付金額がわかる証明書の添付は不要
e-Taxで確定申告をする場合は、寄付金額がわかる証明書添付の省略が可能です。
- 寄附⾦受領証明書
- 寄附⾦控除に関する証明書
寄附金受領証明書は、ふるさと納税の寄付をしたことを自治体が証明する書類で、普段の買い物でいうところの領収書にあたります。
寄付をすると通常自治体から郵送で送られてきます。
寄附⾦控除に関する証明書は、寄付した自治体をすべて記載して1枚になったものです。



もし6自治体に寄付したならば、寄附金受領証明書は6枚!
寄附金控除に関する証明書だったら、たったの1枚で済むので書類の管理の手間もないですよ。
e-Taxで提出して完了
e-Taxで作成した「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」を、そのままe-Tax上で提出すれば確定申告は完了です。
①印刷して税務署に持参
②印刷して郵送
③e-Taxでオンライン提出(スマホやパソコン)
上記のように3つの提出方法がありますが、③のオンライン提出は確定申告書に証明書データを添付して提出できます。>>所得控除のやり方STEP4でみてみる
確定申告は通常2月16日から3月15日までなので、期間内に忘れずにおこないましょう。
オンラインなので、時間を気にせずできますよ。
以上パソコンから、スマホを使って認証してのe-Taxで確定申告する方法を解説しました。



でもパソコンが、お家にない人もいますよね。
実はスマホだけでもできるので、動画も参考にしてくださいね。
「寄附金控除に関する証明書」で確定申告が楽


複数の自治体へ寄付した場合、「寄附金控除に関する証明書」を利用することで、年間の寄付金額を証明する書類が1枚で済みます。
通常「寄附金受領証明書」を用いて確定申告をおこなう場合には、寄付先の自治体ごとに控除申請をする必要がありました。
しかし令和3年以降の確定申告からは、国税庁が指定した特定事業者が発行する「寄附金控除に関する証明書」を添付するだけで、可能になりました。



寄付ごと自治体から送られてくる書類の保管管理や、確定申告時にひとつひとつ入力しなくてはならないので、申請作業が非常に面倒!
寄附金控除に関する証明書は、電子データとしてマイナポータル連携や運営するポータルサイトからダウンロードできます。
「寄付金控除に関する証明書」は、国税庁長官に指定された特定事業者のふるさと納税サイトが発行できますので、ふるさと納税をする際のサイト選びの参考にしてください。
ふるなび、さとふる、楽天ふるさと納税、ふるさとチョイス、ふるさとパレット、ふるさとプレミアム、ふるさとぷらす、セゾンのふるさと納税、ANAのふるさと納税、ふるさと本舗、三越伊勢丹ふるさと納税、JALふるさと納税、au PAYふるさと納税、ふるラボ、ふるさと納税ニッポン!、G-Callふるさと納税、 JRE MALL ふるさと納税、マイナビふるさと納税
確定申告不要!ワンストップ特例制度の特徴とやり方
ワンストップ特例とは、2015年に税制改革で新設された制度です。
2008年にふるさと納税が始まったものの、「確定申告」というハードルのため利用者が増えなかったため、より簡単に利用できるようにと作られたのです。



ワンストップ特例制度を「ドラえもん」で例えるならば・・・
学校から重要な手紙を、ママに渡すのを忘れてしまうのび太。そこで、ドラえもんが秘密道具「手紙スルーボックス」を取り出してあげます。
のび太が、このボックスに手紙を入れると自動的に手紙がママのもとに届き、学校の大切なお知らせがママにもれなく伝わるようにするためです。
つまり「手紙スルーボックス」ならぬ「ワンストップ特例制度」を使うことで、確定申告で控除に必要な税金に関する情報を、自治体を通じて税務署に伝えるようにしたのです。



確定申告とワンストップ特例制度では、還付金に差がでるのか気になる方は「確定申告とワンストップのどちらが得?」を参考にしてくださいね。
ここではワンストップ特例制度のやり方をご紹介します。
まずワンストップ特例申請書を入手しましょう。入手方法は、どの方法でもかまいません。
①ふるさと納税の寄付時に申し込む。
②利用したふるさと納税サイトからダウンロードする。
③総務省の公式HPよりダウンロードする。
④オンライン(PCやアプリなど)で申し込む。
申請に必要な書類を準備します。
・ワンストップ特例申請書
・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証などのコピー)
書類がそろったら、寄付した自治体に提出します。
・郵送の場合は、「必着」になので、土日も計算して投函するようにしましょう。
・記入漏れや必要書類の添付漏れ、書類不備があると申請を受け付けてもらえないので気を付けましょう
うっかり忘れてしまうので、返礼品が届いたら申請しておくといいでしょう。



申請書のダウンロード方法や書き方の見本も参考にしてみてください!
オンライン申請が可能な自治体もある


自治体によってはオンライン申請できるところもあり、マイナンバーカードが手元にあれば手続きが非常に簡単になります。
自治体マイページ、IAM<アイアム>、e-NINSHOなどのサービスを導入している自治体で利用できます。
①自治体マイペ ージ  | ②IAM <アイアム>   | ③e-NINSHO   |
| ・自治体が提供するオンラインサービス。 ・web上で寄附者個人のふるさと納税に関する情報が確認できる。 ・一括申請できる。 | ・公的個人認証アプリ ・スマホのみ利用可能。 ・申請書のQRコードとマイナンバーカードの個人情報を読み取り手続きする。 ・申請は一つずつ行う。 | ・公的個人認証アプリ ・ふるなびサイトを経由して使用。 |
どのサービスを導入しているかは、それぞれの公式ページやふるさと納税の自治体紹介ページなどで確認できます。
IAMと自治体マイページの導入自治体はどちらが多い?


(出典:楽天ふるさと納税)
自治体マイページ、IAMともに2022年から導入されたためどちらも比較的新しいシステムなので、今後増えていくことが予想されます。
自治体マイページとIAMの両方とも使える楽天ふるさと納税HPから見ると、自治体マイページを導入している自治体が若干多く見受けられます。(2023年8月)
ここでは、自治体マイページでの方法を解説します。
用意するもの・マイナンバーカード
・マイナンバーカード発行時のパスワード2つ
(券面事項入力補助用と署名用電子証明書用)
事前にすべきこと・マイナポータルアプリをダウンロード
・自治体マイページのアカウント登録。
自治体マイページのトップ画面のメニューから、オンラインで申請したい寄付先を選択します。
※オンラインワンストップ対応の自治体は一度の操作で一括申請できます。


1回目は、券面事項入力補助用(4桁)のパスワードを入力し本人確認をします。
読み取る際にはマイナポータルアプリが自動で立ち上がります。


2のステップで本人確認をすることにより、住所・氏名・電話番号などの情報も
が自動で入力されます。申請内容とともに間違っていないか確認しましょう。
2回目は署名用電子証明書用のパスワードを入力し、マイナンバーカードを読み取ります。
読み込み終えたら、申請は完了です。
ふるさと納税の確定申告時でよくある質問
まとめ
ふるさと納税による税金の控除を受けるためには、確定申告かワンストップ特例制度を利用しなくてはなりません。
ワンストップ特例制度は、利用するための条件がありますが、仕組みさえ知ってしまえば、本当に簡単なので使わないともったいないです。



あなたがワンストップ特例の利用できるかパターンにあてはまるならば、ぜひとも活用してふるさと納税を楽しんでくださいね!